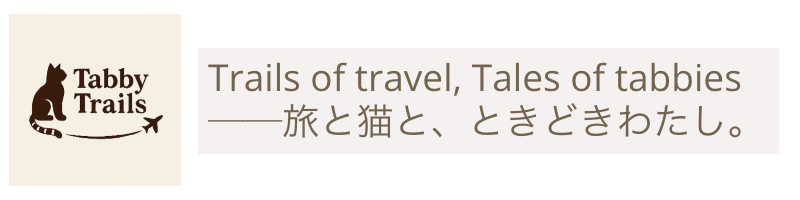「せっかく新しいおもちゃを買ったのに、すぐ飽きてしまった…」
「全然遊ばない…うちの猫、遊び嫌いなのかな?」
こんな悩みを持つ飼い主さん、多いのではないでしょうか?
実は猫は非常に飽きっぽい動物。特におもちゃに対しては興味の持続が短く、せっかく買ってもあまり遊ばない、もしくはそもそも食いつかないということがよくあります。
今回は、そんな **「猫がすぐおもちゃに飽きてしまう問題」**に対して、我が家の猫(アビ助と茶々丸)の経験も交えながら、実際に効果のあった5つの対策をご紹介します。
【対策1】おもちゃは“ローテーション”で使う
猫が飽きる一番の原因は「慣れ」。
いつも同じおもちゃが転がっていると、刺激がなくなり興味を失います。
そこでおすすめなのが、おもちゃのローテーション管理。
たとえば、5種類のおもちゃを週替わりで1つずつ出してあげるだけでも、猫の反応がガラッと変わります。
ポイント:
- 遊び終わったらすぐ片付ける(見えないように収納)
- 1〜2週間後に再登場させることで“新鮮さ”が復活!
- 天日干ししてみる(匂いが分かるのか?新鮮さが復活!)
おもちゃの数を増やす必要はありません。「再会の演出」こそが鍵です。
【対策2】飼い主が“動かし方”を工夫する
同じ猫じゃらしでも、飼い主の動かし方ひとつで猫の食いつきが大きく変わります。
猫は“生き物のような動き”に本能的に反応するため、以下のような動きを試してみてください。
効果的なじゃらし方:
- ピタッと止まる → ジッとした後に素早く動かす(獲物風)
- 障害物の陰からチラ見せ(ハンティング本能を刺激)
- 手元ではなく床や壁際を這わせるように動かす
「遊ばない」のではなく、「動かし方がつまらない」のかも?新聞紙のしたで動かして虫っぽい動きを再現するもよし、ソファ等の陰からちらっと見せるのもウズウズするみたいです。
飼い主自身がちょっと演出家になってみるだけで、猫のテンションが上がりますよ。
【対策3】おやつやキャットフードと組み合わせて“ご褒美化”
おもちゃ単体では食いつかない猫でも、「ご褒美付き」になると話は別です。
例えば:
- おやつが出てくる知育おもちゃ
- 転がすと中からフードが出るボール
- おもちゃの先端にチュールを少しつける(お部屋が汚れるリスクあり)
こういった仕組みを使うことで、**「おもちゃ=嬉しいもの」**と猫にインプットさせることができます。
飽きる前に、「遊びたい」と思わせるトリガーをつくるのがポイントです。
【対策4】“新しい素材”や“音”を取り入れた手作りおもちゃも試す
意外と猫が夢中になるのが、身近な素材を使った手作りおもちゃです。
市販品に飽きてしまったら、以下のような素材を取り入れてみてください。
おすすめ素材例:
- 紙袋(ガサガサ音+隠れるのが楽しい)
- アルミホイルを丸めたボール(コロコロ+光の反射)
- トイレットペーパーの芯(中におやつを隠すと知育にも◎)
“非日常感”を感じる音や触感が、猫の興味を呼び起こします。
お金をかけなくても、「猫の五感を刺激する」ことが重要なんです。
【対策5】“遊びの時間”をルーティンにする
猫にとって、おもちゃ遊びは習慣化されていないと面倒に感じることも。
そのため、毎日決まった時間に遊ぶ習慣をつけることで、猫が「今は遊ぶ時間だ」と認識しやすくなります。うちの茶々丸は、遊びの時間になるとおもちゃがしまってある戸棚の前でスタンバイしてます(笑)
特におすすめのタイミングは:
- 朝ごはん前(狩猟本能が活性化)
- 夜の寝る前(運動で落ち着きやすくなる)
ルーティンを取り入れることで、「おもちゃ=面白いことが始まる合図」となり、飽きるどころか楽しみにするようになります。
まとめ|猫が飽きるのは当然。工夫次第で遊びは再び楽しくなる!
猫がすぐおもちゃに飽きるのは、決して珍しいことではありません。
でもちょっとした工夫で、同じおもちゃでも再び楽しく遊んでくれるようになります。
今回ご紹介した「猫 おもちゃ 飽きる 対策 5選」はこちら:
- おもちゃはローテーションで使う
- 動かし方を工夫する
- ご褒美要素を取り入れる
- 素材や音で新鮮さを演出
- 遊び時間をルーティン化する
飽きるたびに新しいおもちゃを買う必要はありません。
「遊び方を変える」ことが最大の対策です。
我が家のアビ助と茶々丸も、実は飽きっぽいタイプ。でも上記の方法を取り入れてから、また元気に遊んでくれるようになりました。猫と一緒に「遊び」をもっと楽しみましょう♪